
クリスマスの本場北欧から古き良き時代のアメリカに伝わった、
伝統的なクリスマスの迎え方をご紹介します。
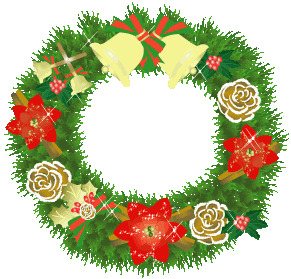

11月もそろそろおわりに近い朝の様子を想像してください。
もう20年以上も昔のことです。
どこかの田舎町のひろびろとした旧家の
お勝手のありさまを考えてみてください。
「おやまあ、フルーツケーキの支度にかかるにはもってこいのお天気だよ」
カポーティの「クリスマスの想い出」の書き出しです。
カポーティと言えばあの「ティファニーで朝食を」の著者。
「クリスマスの想い出」は、その「ティファニーで朝食を」
(新潮文庫・龍口直太郎訳)に一緒に収まっている短編小説です。
アメリカの田舎町。旧家に親戚が集まり暮らしています。
60いくつかのおばあちゃんと7さいのぼくは、
ぼくが、ものごころついたときから二人で暮らしています。
同じ屋敷には親戚が何人かすんでいるけど、
威張っていて、ちょいちょいぼくたちを泣かせます。
そんなおばあちゃんとぼくの楽しみは、年に一度のクリスマス。
11月の終わりになると森へ「ピカンの実」を拾いに行き、皮を剥いたり、
街へ買い出しへいったり、急にいそがしくなります。
サクランボに、シトロン、ショウガにバニラ、ハワイのパイナップルの缶詰、
ラインドに乾ぶどうにクルミにウイスキー。
そのうえたまげるほど、どっさりの小麦粉、バター、数えきれぬほどの卵、香料と薬味。

ところがふたりは素寒貧(すかんぴん)。
材料を買うお金を1年かけてすこしずつ、貯めていました。
ガラクタ市を開いたり、懸賞に応募したり。
ほかにも思い出したくもない仕事をして貯めた、
わずかなお金をすべて使ってフルーツケーキを焼くのです。
「石炭と薪をくべた料理用ストーブが、まるでかぼちゃのちょうちんのように真っ赤に焼け、
卵の泡立て器がおどり、さじがバターと砂糖のはいった鉢の中でキリキリ舞いを演じます。」
「バニラの甘い香りがあたりに立ちこめ、ピリッとしたショウガの匂いもまざって、
プーンとしたおいしい匂いが屋敷中に、煙突から隣近所へも、漂ってゆきます。」
こうして4日間かけて焼き上がった31個のフルーツケーキ。
「そんなにたくさん焼いてどうするの?」
親しい人にプレゼントするのです。
それは、となり近所のひとたちだけではなく、実際ケーキの半分以上は、
たぶん一度しか会ったことのないひととか、
おそらく一度も会ったことのないひとたちに贈るつもりでこしらえたのでした。
なんとなしに、心ひかれたひとたちに食べてもらうつもりでこしらえたのでした。
 たとえば、ルーズベルト大統領、
たとえば、ルーズベルト大統領、
去年、町にやってきた牧師、
1年に2回やってくる包丁の研ぎ屋、
バスの運転手、
たまたま家のそばでクルマが故障して
1時間ほどしゃべったカリフォルニアの夫婦。
そうして、出来上がったケーキを届ける小包代を支払うと、すっかり財布の底をはたき、
ふたりは再び文無しに。
それでもめげすに、森でとびっきりのツリー用のもみの木を切りだしたり、
そのツリーを高く買うと言われても、ゆずらなかったり。
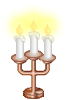
クリスマスといえば、北欧のイメージですが、ヨーロッパから苦労して移住した人々の
年に一度のお楽しみとして、アメリカの古き良き時代には、こころあたたまる
こんな話があふれていました。
想いを伝えるために、自分たちに出来る精一杯のプレゼントをつくって、
1年に一度、贈りたい人に届ける。クリスマスを迎えられる喜びを、分かち合うために。

それが、日本へ伝わる頃には「ケーキ、ごちそう、プレゼント」だけが、一人歩きしてしまいました。
人と人とのつながりが、希薄にならざるおえない今の時代だからこそ、
こんなクリスマスの迎え方に、心惹かれるのかもしれませんね。
物があふれていることが、豊かなこと、幸せと感じることには決してつながらないと、
あらためて、考えさせられました。
今年のクリスマスの夜は、すこしだけこの本のことを思い出して、すごしてみようと思います。
最後まで読んでいただいたあなたに、メリークリスマス。

コメント